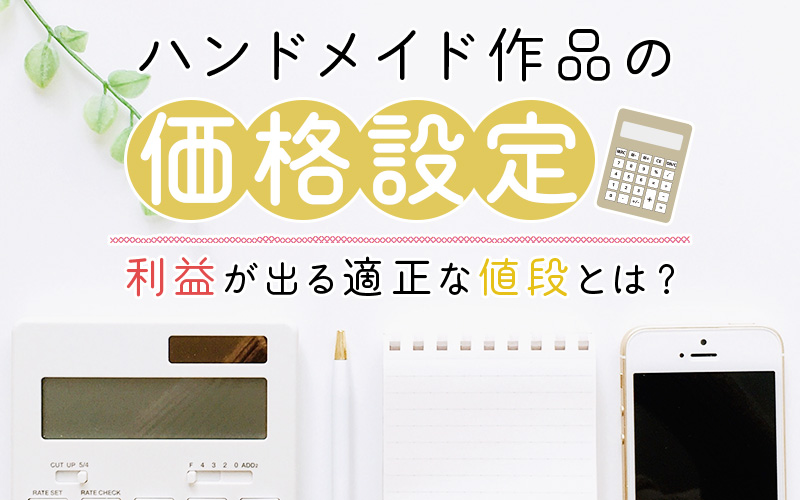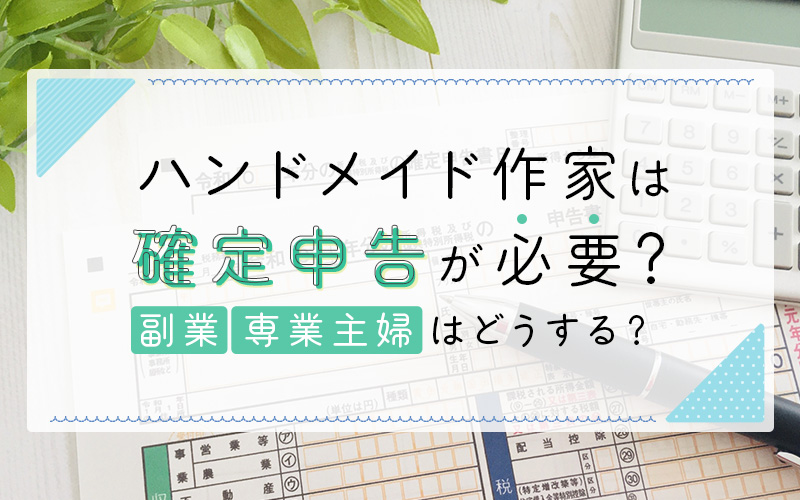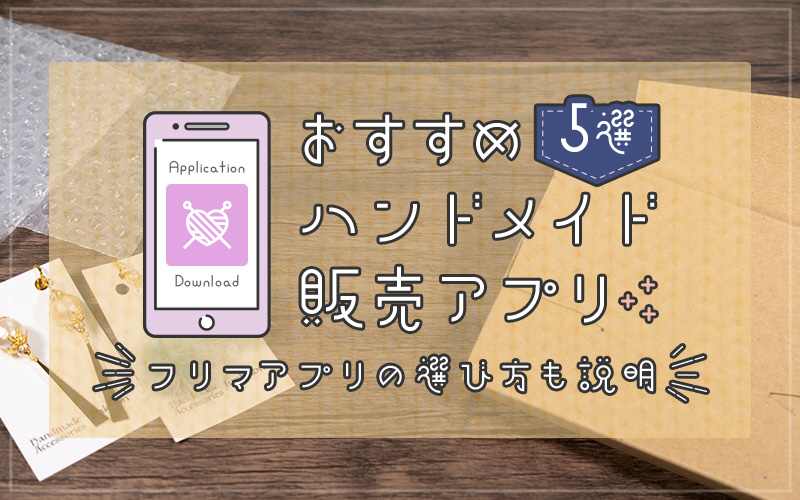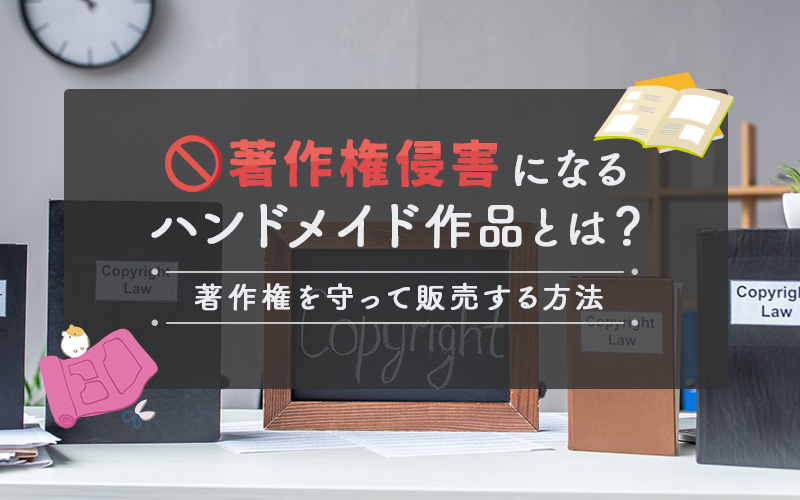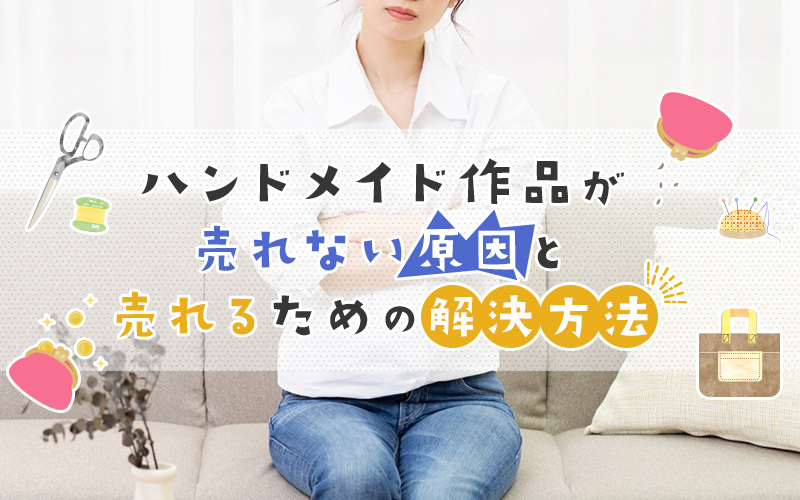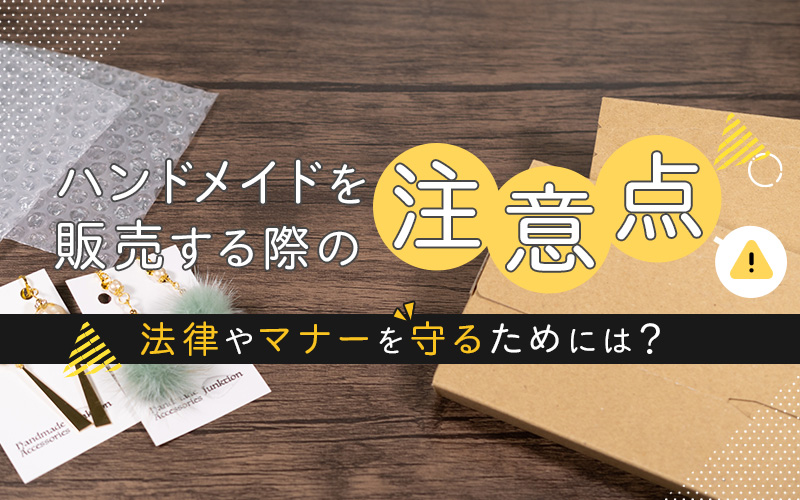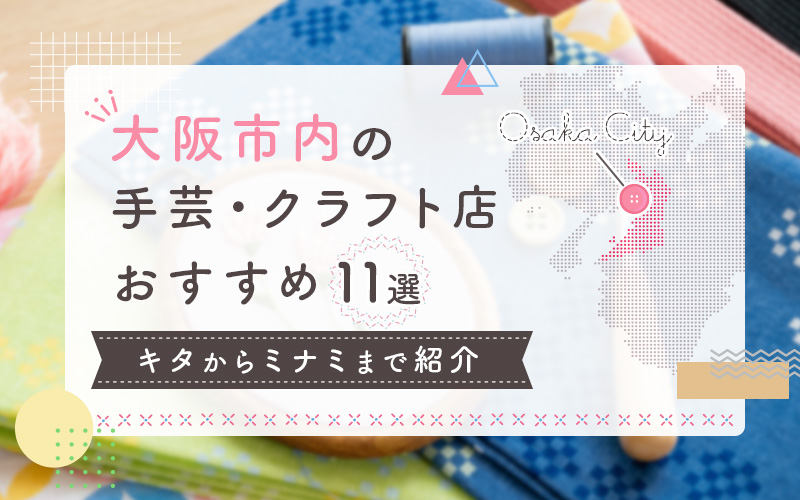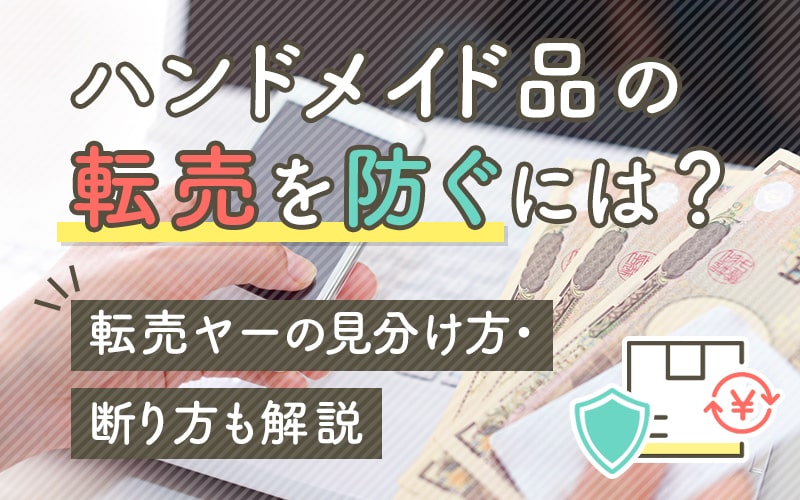カテゴリー【ハンドメイド】の記事一覧
ハンドメイド 1,472 view
ハンドメイド作品の価格設定!利益が出る適正な値段とは?
ハンドメイド作品を出品するとき、価格設定で悩むケースは多いのではないでしょうか。ハンドメイド作品の出品で利益は出したいものの、買ってもらえない価格にはしたくないものです。価格設定に迷ったときに備え、適正な価格の設定方法や […]
2021.08.20ハンドメイド 1,594 view
ハンドメイド作家は確定申告が必要?副業・専業主婦はどうする?
近年では、自分で作成したハンドメイド作品をフリマアプリ・サイトなどでネット販売して、収入を得ているハンドメイド作家も多くいます。 ハンドメイド作家として、毎月収入をしっかり得ているのであれば、「確定申告」についても考えて […]
2021.08.20アクセサリーパーツ販売サイトおすすめ25選|ハンドメイドに最適!
アクセサリーのハンドメイドに必要なアクセサリーパーツは、インターネットの販売サイトで購入することが手軽でおすすめです。アクセサリーパーツの販売サイトは数多く存在し、サイトごとに色とりどりのパーツが用意されています。 販売 […]
2021.08.20【初心者向け】ハンドメイドの販売方法と売上アップのコツ!
自作のアクセサリーや生活雑貨などをネットショップで売るハンドメイドの販売は、趣味や副業の一つとして人気を集めています。しかし、いざ販売を始めようと思っても、何をどのように進めたらいいのか分からない方も多いのではないでしょ […]
2021.08.20おすすめハンドメイド販売アプリ5選!フリマアプリの選び方も説明
インターネットの利用が幅広い世代で一般化した現在、ハンドメイド作品を気軽に販売できるフリマアプリも多数登場しています。フリマアプリと言うと、CMや広告などでもよく見る利用者の多いサービスを思い浮かぶ方も多いでしょう。しか […]
2021.08.20ハンドメイド 1,985 view
著作権侵害になるハンドメイド作品とは?著作権を守って販売する方法
ハンドメイド作品を販売する際、著作権を侵害する場合があります。「心を込めて作った作品を販売したのに権利を侵害してしまった」ということにならないためにも、前もって著作権侵害となる具体例を知っておくことが必要です。 当記事で […]
2021.08.20ハンドメイド 1,069 view
ハンドメイド作品が売れない原因と売れるための解決方法!
ハンドメイド作品は、手作り感を好む人や市販にはない個性を求める人に人気の商品です。しかし、突出した人気作家が出る一方で、なかなか評価が上がらない作家も少なくありません。時間と労力をかけて一生懸命作った作品が、誰にも手に取 […]
2021.08.20ハンドメイド 731 view
ハンドメイドの宣伝におすすめのSNS5つ|活用法・参考例も
ハンドメイド作品の宣伝には、SNSの活用が効果的です。SNSではハンドメイド活動の情報を発信する他、フォロワーの傾向や閲覧数を作品制作における目安として利用することも可能です。しかし、ハンドメイド作品の宣伝方法や、SNS […]
2021.08.20ハンドメイド 1,541 view
ハンドメイドを販売する際の注意点!法律やマナーを守るためには?
近年はフリマアプリやハンドメイド品販売サイトが増え、ハンドメイド作家として活躍する人が増えています。副業としても人気のハンドメイド作品販売は、ネット販売のマナーや法律についてよく知らないまま商品を売ると思わぬトラブルを招 […]
2021.08.20
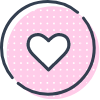


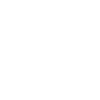

 CATEGORY
CATEGORY