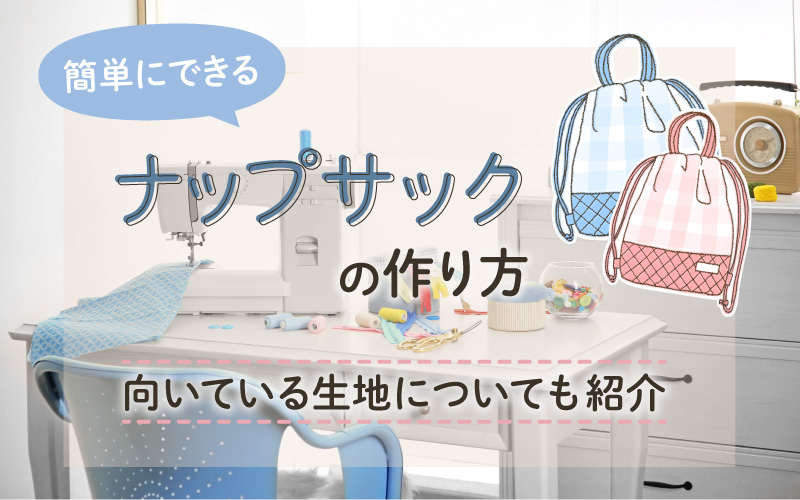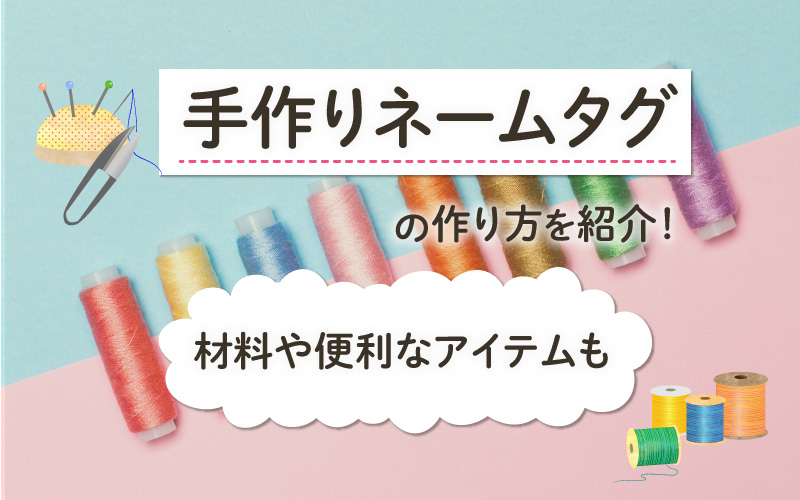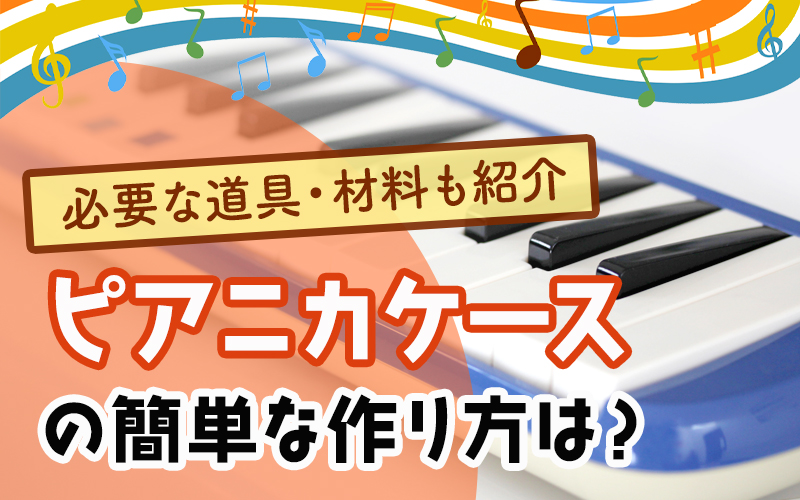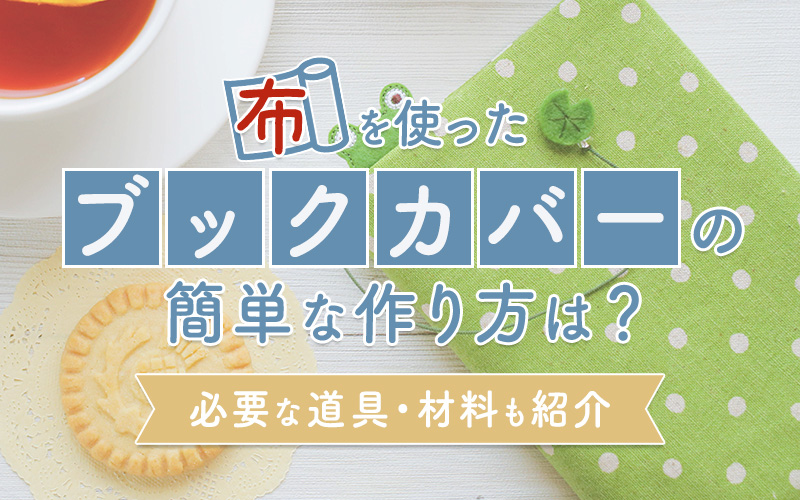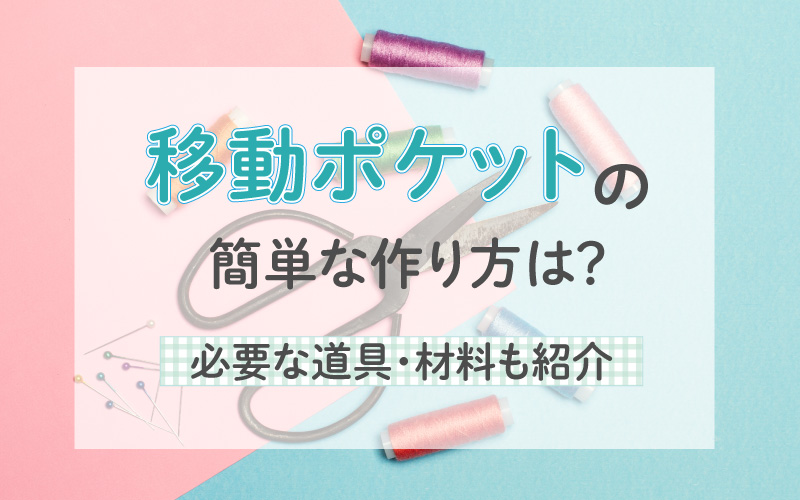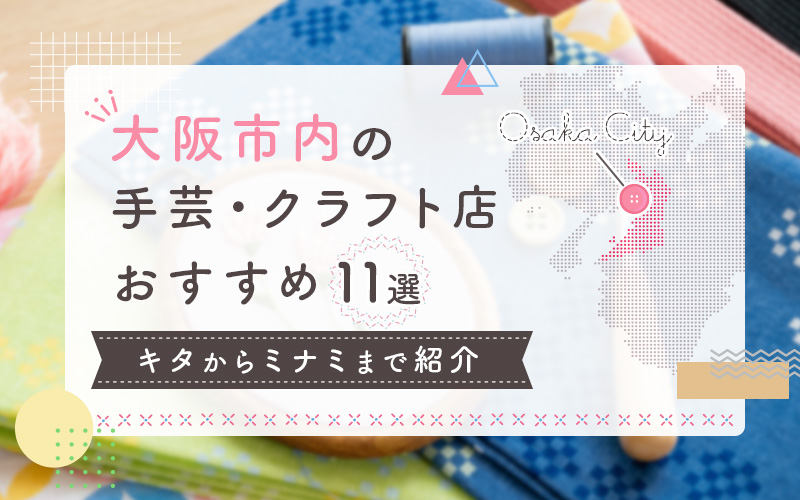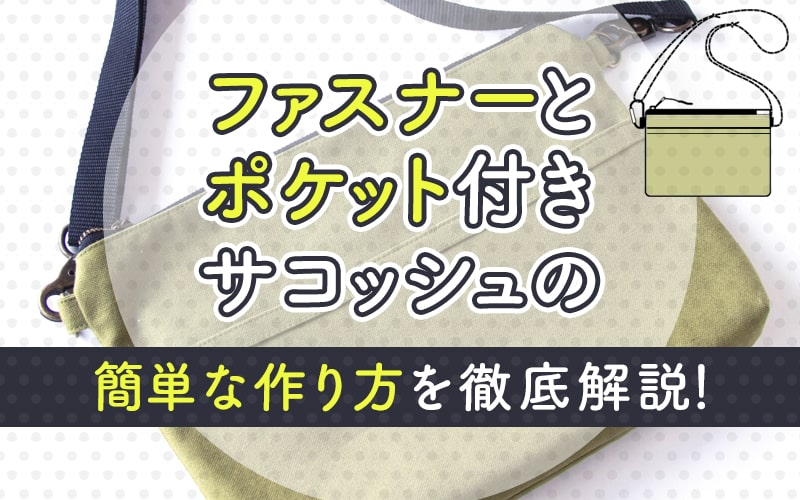カテゴリー【ハンドメイド】の記事一覧
ハンドメイド 852 view
簡単にできるナップサックの作り方|向いている生地についても紹介
ナップサックは巾着リュックとも呼ばれる、小型で軽量のリュックサックです。肩ひもを絞ることで巾着袋のように簡単に口を閉じられ、お子さんの体操服袋や着替え袋として活躍します。リュック型なので、両手が空くところも便利です。ナッ […]
2024.07.19ハンドメイド 567 view
手作りネームタグの作り方を紹介!材料や便利なアイテムも
子ども用ネームタグとは、子どもの名前や緊急連絡先などの情報を記載した小さな名札のようなものです。 子どもの名前を視覚的に確認できるため、先生が呼びかける際に便利です。着替えの服などが混同しないよう、区別するのにも役立ちま […]
2024.07.19ハンドメイド 140 view
ハーバリウムのハンドメイドに必要な材料は?売っているお店も解説
ハーバリウムは、花材・密閉できる透明な容器・ハーバリウム用のオイル・ピンセット・ハサミなどがあれば、簡単にハンドメイドできます。ハーバリウムは、誕生日や記念日などのプレゼントにも最適です。世界に1つだけのオリジナルハーバ […]
2024.07.19ハンドメイド 227 view
ピアニカケースの簡単な作り方は?必要な道具・材料も紹介
ピアニカは、ほとんどの小学校で入学後に一斉購入が必要になります。身体の小さな低学年の子供にとっては、ランドセルと一緒にピアニカも持ち運ぶのは大変です。少しでも子供の負担を減らしてあげるには、ピアニカケースを作ってあげると […]
2024.07.19ハンドメイド 202 view
ファブリックパネルの簡単な作り方は?必要な道具・材料も紹介
毎日過ごす自宅のインテリアにこだわれば、より豊かな暮らしを実現できます。多種多様なインテリアアイテムがある中で、今回紹介したいのが「ファブリックパネル」です。 ファブリックパネルは、木製パネルにファブリック(布)を貼り付 […]
2024.07.19ハンドメイド 623 view
布を使ったブックカバーの簡単な作り方は?必要な道具・材料も紹介
読書が趣味という方の中には、バッグに本を入れて持ち運んだり、カフェや電車で読んだりすることも多いのではないでしょうか。そういった場合は、ブックカバーを装着するのがおすすめです。 ブックカバーを装着すれば、本が傷つくのを防 […]
2024.07.19ハンドメイド 992 view
【初心者向け】おしゃれなターバン型ヘアバンドの作り方を解説
ヘアバンドはヘアスタイルを整え、髪の広がりを抑えつつ、キュートなアクセサリーにもなります。市販品を買うのもよいですが、ターバン型のヘアバンドならハンドメイド初心者でも簡単に裁縫でき、自分が好きな色柄の布で作れます。余った […]
2024.07.19ハンドメイド 111 view
マスクケースを手作りしたい!必要な道具・材料や簡単な作り方を解説
新型コロナウイルスの影響により、以前にも増してマスクの存在がより身近なものになりました。外食時にマスクを外すときや、ストックを常に持ち運びたいときは、マスクケースがあると便利です。 使用中のマスクやストックのマスクをケー […]
2024.07.19ハンドメイド 250 view
レッスンバッグの作り方!手提げバッグや通園バッグ、絵本袋にも
入園・入学準備をする際、用意しておかなければならないアイテムの1つとして、レッスンバッグ・通園バッグが挙げられます。入園・入学以外にも、ピアノや塾といった習い事に通う場合、レッスンバッグがあると便利です。 当記事では、レ […]
2024.07.12ハンドメイド 204 view
移動ポケットの簡単な作り方は?必要な道具・材料も紹介
移動ポケットは、ズボンやスカートなどのウエスト部分にクリップで取り付けて使用する、簡易的なポケットです。ハンカチやティッシュ、マスクなどの小物を収納できます。 洋服にポケットがない場合でも、小物を持ち歩くことができる点や […]
2024.07.12
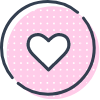


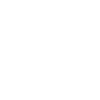

 CATEGORY
CATEGORY